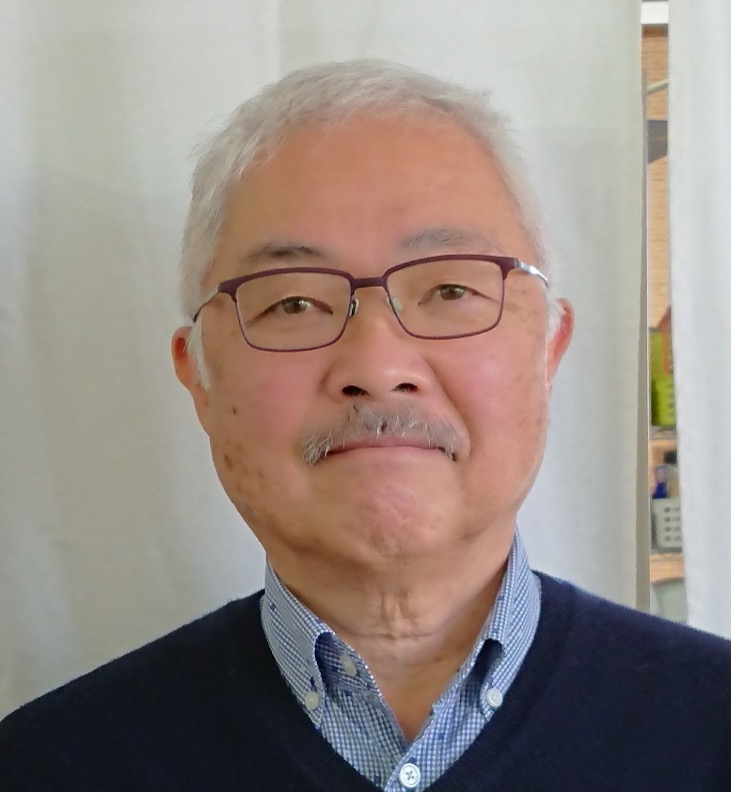本記事は、1971年の「将棋世界」に寄稿されたアレックス・ランドルフのコラムを書き起こしたものです。(原稿提供:日本将棋連盟)

チェスと将棋の優劣を論ずることは無意味である。我々が言えることは、両者は親戚であること、先祖が同じであるから非常に似ており、別個の進化をたどったから非常に異っている、ということだけである。将棋とチェ スの共通の先祖はチャトランガと云う昔のイ ンドのゲームであることはよく知られてい る。だが昔といっても、最古の記録が七世紀頃のものだからこの驚くべきゲームの誕生はそれ程古いものではない。異った方角へ岐れて行き、異った進化をたどったチャトランガの原型については不明な点も多いが、後世の同族ゲームに見られる種々の特徴は当然原型に存在した筈である。それ故に我々が相当な確信を以て言えることは、それが二つの軍隊を戦闘配置した方形の盤上で争われたゲームであり、下方に将校の一列、上方に歩兵の一 列があったこと、歩兵は前方に一格だけ動き、 将校は各自異る動きをしたこと、競技者は交 互に一手づつ指したこと、取った駒は盤上から除いたこと、将校列の隅から二番目の駒は馬と呼ばれたこと、馬は読者の御承知の特殊な動きで他の駒を跳び越せたこと、そして最後に、第一列中のまわりに一格だけ動く駒が最重要な駒であり、それの捕獲がゲームの唯一の目的であったことである。以上の説明をチェスプレヤーは勿論チェスのそれと解し、 将棋プレヤーは将棋のそれと解する。然し両者が今日その他の点で如何に異っているかを考えると、これは誠に興味深い。インドから西方の道をとったこのゲームはイラン、イスラム帝国、更に北アフリカ等を経て西紀千年頃ヨーロッパに達した。チェスの歴史のうちこの部分は文献も、学者の研究も豊富である。シャトランデと呼ばれるチェスはイスラム世界で高く評価され、莫大な関係文書と職業選手団を産み、彼等は技量を公開し、バグダードのカリフに召されて御前試合を行った。このことはチェスの歴史上初めてこのゲ ームの価値が認められ、それが正しく値いする基盤に立ったことであり、日本に於ける将棋の隆盛及び西欧に於ける近代チェスの繁栄をみる迄は二度と起らぬ現象であった。約八百年栄え今でも孤立した地方、特にアピシニアとマダガスカルで行われているこのゲームの特徴は、キングが極めて弱い大臣(将棋の金将となり、チェスのクインとなった)と一層弱い象(将棋の銀将及びチェスのビショッ プの前身)に囲まれている『ソフト』な中央を、強力なルークと馬が両翼から援護していることにある。チャトランガの他のルートについては西方路程は明らかではなく、失われたリンクも多い。しかし一つの枝が古来の北 東路をとって中国及び朝鮮将棋となり、別の枝が南東路を進んでビルマ、タイ、マレー、 並びにインドネシアの島々に向ったことは明らかである。美しいタイのマクルクは今に昔 の姿をとどめる南東チェスの一つであり、その他の類似チェスが今もビルマやインドネシ ァで行われていると云う。では将棋はどこから来たのか
将棋は他の多くの文化財と共に中国、朝鮮ルートから渡来したと考えるのは自然であ る。しかも実際にこれを支持する若干の証拠もある。それは中国及び朝鮮将棋だけにある 三つの特徴が将棋と共通するからであり、そ の特徴とは(一)駒が平らで文字により区別されること、(二)白盤は八十一格であり、九行の中央にキングのあること、(三)歩は前進し、前の駒を取ることである。以上の点は明らかに将棋と隣接大陸のゲームとのリンクを示してい る。然し乍ら一層印象的ですらあることは、 中国及び朝鮮将棋の他の奇妙な特徴、即ち特 に中国将棋の中央の『河』及び前進して配置され且つ不思議な程無防備な歩兵、そして最 も重要な、中国及び朝鮮将棋に共通のキングを終世禁錮して置く奇妙な『城』のいづれも が渡来しなかったという事実である。更に又その駒の当初の配置及びそのスピリットに於 て、将棋は中国、朝鮮以外のチェスにより近 い関係がありそうに思われる。では将棋と南 東同族とを結ぶリンクがあるか? 私は在ると信ずる。小さな証拠は歩が三列目より出発し敵の三列目に至って昇格することで、これはタイのマクルークと全く同じである。大きな証拠とは、将棋がより南方から渡来したという決論を見逃すことの出来ない程強力なもので私はそれを象の問題と呼び度い。チャトランガの象は馬の隣りに位置する故に、それはチェスのビショップ及び将棋の銀将となった駒である。象の本来の動き方は不明であるが、古代ペルシアのチェス及び現在の中国将棋の象から演繹して斜に二格動いたと考えら れる。兎に角ゲームが南東に進むにつれ、象の動き方はより現実的になった。それは斜めに一格づつ及び前方一格、即ち象の四足と鼻に照応する所謂五方角の動きに変じたのである。之は現在のタイのマクルークの駒の動きであり、云うまでもなく銀将である。正に偶然以上のものである。物語りが正にこれから佳境に入るところで小稿の第一部を終る。というのは第一部では私は周知の事柄を、やや違った形で物語ったに過ぎないからである。 そして私は、日本側の資料に不案内の為に、 多くの誤認を犯したかも知れないし、又は私にだけ興味があり私にだけ新奇であるが、実は判り切った事を述べたのかも知れぬ、と思う。
(中島一郎訳)